横浜で相続した空き家が増加中──放置せずに早めの対策を
相続をきっかけに、自宅や実家を引き継ぐ方が増えています。
しかし、「誰も住まない家をどうするか」という問題に直面する人も少なくありません。
特に横浜のように住宅が密集し、地価が高い地域では、空き家を維持することが思った以上の負担となるケースが多く見られます。
実際、相続後に「とりあえずそのまま」にしてしまう家庭も多く、結果的に何年も放置されてしまうこともあります。
ここでは、横浜で相続した家が空き家になってしまう代表的な理由と、そこから生まれる悩みを整理してみましょう。
誰も住まなくなった実家を相続して困っている人が増えている
かつては「親の家を子どもが引き継ぐ」のが一般的でしたが、現在ではライフスタイルの変化により、相続後も誰も住まない家が急増しています。
仕事の関係で他県に住んでいたり、すでに自宅を所有しているケースも多く、「使う予定がない家」を相続することになるのです。
横浜市内でも、相続によって家を引き継いだものの、
- 自分や家族が住む予定がない
- 管理やメンテナンスに手が回らない
- 相続人同士で活用方針が決まらない
といった理由から、空き家のまま放置されているケースが増えています。
その結果、空き家は年々老朽化し、資産どころか「負動産(ふどうさん)」となってしまう懸念もあります。
維持費・固定資産税・管理の負担が重くなりやすい
相続した家をそのまま維持するには、意外と多くの費用がかかります。
固定資産税や都市計画税はもちろん、年に数回の清掃や草刈り、修繕費などを考えると、年間で数十万円の負担になることもあります。
特に横浜市のように地価が高い地域では、固定資産税の額も大きくなりがちです。
さらに、建物を放置して老朽化が進むと、雨漏り・倒壊・不法侵入などのリスクも発生し、近隣トラブルの原因にもなります。
「まだ使えるから」「もったいないから」と保留にしていても、維持コストとリスクは確実に積み上がるため、早めの対応が必要です。
売るか残すかで家族間の意見が分かれるケースも
相続した家をどうするかを決める際に、最も多いのが家族間の意見の不一致です。
「思い出があるから残したい」という感情面の意見と、「維持費がかかるから売りたい」という現実的な意見がぶつかることは珍しくありません。
また、相続人が複数いる場合、所有権の分割や登記の手続きで話が進まないケースもあります。
結果として「誰の名義にするか」「売るタイミングをどうするか」が決まらず、空き家のまま時間だけが過ぎてしまうのです。
こうした問題を放置すると、税制上の特例(相続空き家の3,000万円控除など)が使えなくなることもあり、経済的な損失にもつながります。
家族間で感情的になりすぎず、専門家を交えて冷静に話し合うことが、最初の一歩といえるでしょう。
相続した空き家を放置するとどうなる?リスクとデメリットを解説
「相続したけれど、まだどうするか決めていない」「とりあえず空き家のままにしている」という方は多くいらっしゃいます。
しかし、空き家を長期間放置することは、思った以上に大きなリスクを伴います。
横浜市でも年々「管理不全の空き家」が増加しており、行政からの指導や近隣トラブルにつながるケースも少なくありません。
空き家を放置してしまうことで起こり得る主なリスクを3つに分けて解説します。
倒壊・火災・不法侵入などのトラブルリスク
空き家の最も深刻なリスクは、安全性の低下と犯罪リスクの増加です。
人が住まなくなると、建物の換気がされず湿気がこもり、木材の腐食やシロアリ被害が進行します。
屋根や外壁が劣化すれば、台風や地震で倒壊する危険性もあり、周囲への被害や賠償責任を負う可能性もあります。
また、放置された家は人の出入りが少ないため、放火や不法侵入、ゴミの不法投棄といったトラブルの温床になりがちです。実際に横浜市内でも、空き家から出火した火災や、無断で住み着くケースが報告されています。
このようなトラブルが発生すると、所有者の責任が問われることもあり、「放置していたらいつの間にか大きな損害に…」という事態にもなりかねません。
「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍に
2015年に施行された「空家等対策特別措置法」により、管理が不十分で危険と判断された空き家は、
行政から「特定空家」に指定される可能性があります。
「特定空家」とは、以下のような状態の建物を指します。
- 倒壊の危険がある
- 著しく衛生状態が悪い
- 景観を著しく損なっている
- 周辺に悪影響を及ぼしている
一度「特定空家」に指定されると、これまで住宅用地として軽減されていた固定資産税の特例(1/6軽減)が解除されます。
つまり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるということです。
さらに、行政からの指導・勧告を無視すると、最終的に「行政代執行(強制解体)」が行われ、その費用を所有者が負担することもあります。
放置すればするほど、お金も時間も失う結果になってしまうのです。
資産価値の下落と売却チャンスを逃す危険性
空き家を放置することで、資産価値がどんどん下がっていくのも見逃せないリスクです。
築年数が経過するほど建物の価値は減少し、老朽化が進むと「土地としてしか売れない」状態になることもあります。
また、放置期間が長くなるほど、登記・相続・境界などの問題が複雑化し、売却の際に余計な手間や費用が発生します。
一方で、横浜市では再開発エリアや住宅需要が高い地域も多く、早めに売却すれば有利な価格で売れる可能性もあります。
つまり、「今はまだ大丈夫」と先送りにしている間に、
- 税金が増える
- 修繕費がかさむ
- 市場価値が下がる
という三重苦に陥る危険があります。
空き家は“動かない資産”ではなく、時間とともに価値を失っていく負債になり得る存在です。放置せず、早めの売却・活用を検討することが、最も賢い選択といえるでしょう。
横浜で相続空き家を売却するまでの流れと手続きのポイント
相続した空き家を売却したいと思っても、「何から始めればいいのかわからない」という方は多いでしょう。実際、相続に関わる売却は、通常の不動産取引よりも手続きや関係者が多く、注意点も多いのが特徴です。
しかし、流れを正しく理解しておけば、スムーズに手続きを進めることができます。ここでは、相続した空き家を売却するまでの一般的な5つのステップを解説します。
① 相続登記を完了させて名義を変更する
まず最初に行うべきは、相続登記(名義変更)です。亡くなった方(被相続人)名義のままでは、その不動産を売却することはできません。
相続登記では、相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を準備し、司法書士に依頼して法務局で登記手続きを行います。
なお、2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に申請しないと過料(罰金)が科される可能性もあります。
そのため、相続が発生したらできるだけ早く登記を済ませることが重要です。
② 相続人全員で売却方針を決定する
不動産を相続した場合、相続人全員の同意が必要です。
- 売却するのか
- 保有するのか
- 誰が管理するのか
を話し合い、全員で合意を得ることが次のステップにつながります。
遺産分割協議書を作成しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
また、複数の相続人が意見を分けて対立している場合は、第三者(司法書士・弁護士・不動産会社など)を交えて冷静に整理することが大切です。
早めに方向性を決めておくことで、スムーズに査定や売却活動に移ることができます。
③ 不動産会社に査定を依頼して相場を把握
方針が決まったら、不動産会社に査定を依頼しましょう。
査定は無料で行ってくれる会社が多く、物件の現況や立地、築年数などをもとにおおよその売却価格を算出してくれます。
このとき、1社だけでなく複数社に査定を依頼するのがおすすめです。会社ごとに得意エリアや販売力が異なるため、比較することでより正確な相場がわかります。
特に横浜市内では、地元に強い会社ほどエリアごとの相場感を把握しており、より適切な価格を提示してもらえる傾向があります。
④ 売却方法を選ぶ(仲介・買取)
査定結果をもとに、どの方法で売却するかを選択します。
主に「仲介」と「買取」の2種類があります。
- 仲介:不動産会社が買主を探し、市場で販売する方法。相場に近い価格で売れる可能性が高い。
- 買取:不動産会社が直接買い取る方法。相場よりやや安くなるが、早く現金化できる。
相続した空き家が老朽化していたり、早く処分したい場合は「買取」が向いています。一方で、状態が良く高値を狙いたい場合は「仲介」が適しています。
不動産会社に両方の見積もりを出してもらい、目的に合った方法を選ぶのがポイントです。
⑤ 契約・引き渡し・確定申告までの流れ
買主が決まったら、いよいよ売買契約の締結と引き渡しです。この際、登記書類や印鑑証明書などの正式な書類が必要になります。売買契約書を交わし、代金の受け取りと同時に物件を引き渡せば、売却手続きは完了です。
しかし、ここで忘れてはいけないのが確定申告です。空き家の売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合、翌年の2月16日〜3月15日の間に申告を行う必要があります。
また、「相続空き家3,000万円特別控除」が使える場合は、このタイミングで適用を申告します。
税理士や不動産会社にサポートしてもらえば、手続き漏れなくスムーズに進めることができます。
相続した空き家を売却する3つの方法と特徴を比較
相続した空き家を売却する場合、主な方法は「仲介」「買取」「解体・更地化して売る」の3つです。
どの方法を選ぶかによって、売却までのスピードや手取り額、手間が大きく変わります。
それぞれの特徴を理解し、「自分の目的に合った売却方法」を選ぶことが、スムーズで後悔のない売却につながります。
① 仲介で売る(相場重視・時間をかけて高く売る)
もっとも一般的な方法が、不動産会社に仲介を依頼して市場で買主を探す方法です。
売主が不動産会社に販売活動を依頼し、買主が見つかれば契約を成立させます。
仲介の最大のメリットは、相場に近い価格で売れる可能性が高いことです。
エリアの需要が高く、建物や土地の状態が良ければ、希望価格に近い金額での成約も十分期待できます。
ただし、買主が見つかるまでに時間がかかる場合があり、売却期間が数ヶ月〜半年以上に及ぶこともあります。また、売却成立時には仲介手数料(最大で売却価格の3%+6万円+税)が発生します。
こんな人におすすめ
- 少しでも高く売りたい
- 売却まで急いでいない
- ある程度建物が使える状態
② 買取で売る(スピード重視・現況のまま現金化)
「早く手放したい」「老朽化していて修繕が難しい」といった場合に向いているのが、不動産会社による買取です。仲介とは異なり、業者が直接物件を買い取るため、買主を探す手間がなく即現金化できるのが最大の特徴です。
最短で1週間ほどで契約・決済が完了することもあり、相続した家を早く整理したい人や、遠方に住んでいる人にも最適です。
さらに、残置物(家具や家財)をそのままでもOK、老朽化していてもそのまま買い取ってくれるケースが多いため、手間を最小限に抑えられます。
一方で、買取価格は市場相場より1〜2割ほど安くなる傾向があります。
それでも、早く確実に現金化できる安心感を考えると、多くの方にとって合理的な選択といえるでしょう。
こんな人におすすめ
- 相続後すぐに現金化したい
- 建物が老朽化している・片付けができない
- 売却を近隣に知られたくない
③ 解体・更地化して売る(土地の価値を最大化)
建物の老朽化が進み、修繕やリフォームでは対応が難しい場合は、解体して更地にしてから売却する方法があります。
更地にすることで買主が自由に建築計画を立てやすくなり、土地としての価値が最大限評価されるのがメリットです。
横浜市内でも、特に住宅需要が高いエリア(港北区・青葉区・戸塚区など)では、更地化によって買い手が増えるケースが多く見られます。
また、「古家付き」よりも「更地」の方が、広告上の印象が良く、スムーズに契約へつながる傾向があります。
ただし、更地にすると住宅用地の固定資産税軽減(1/6特例)が外れるため、税金が増える点に注意が必要です。また、解体費用として100万〜300万円前後かかるのが一般的です。
不動産会社によっては、解体費を立て替えたり、売却時に差し引いて清算するプランもあります。事前に複数社から見積もりを取り、費用とリターンを比較した上で判断しましょう。
こんな人におすすめ
- 建物の劣化が激しく再利用が難しい
- 土地として高く売れる立地
- 解体費用も含めてトータルで整理したい
このように、空き家の売却には「高値で売る仲介」「早く売る買取」「資産価値を高める更地化」という3つの方向性があります。
それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った売却スタイルを選ぶことが成功のカギです。
相続空き家の売却で使える税制優遇「3,000万円特別控除」とは
相続した空き家を売却する際、「思ったより税金がかかるのでは?」と心配される方が多いでしょう。
実際、空き家の売却益(譲渡所得)には所得税・住民税がかかりますが、一定の条件を満たすことで最大3,000万円までの特別控除が受けられます。
これは「相続空き家の3,000万円特別控除」と呼ばれ、条件を満たせば大きな節税効果を得られる制度です。
ここでは、その概要と対象条件、申請方法を詳しく見ていきましょう。
「相続空き家の特別控除」とは?節税の仕組みを解説
「相続空き家の特別控除」とは、被相続人(亡くなった方)が住んでいた住宅を、相続人が相続後に売却した場合に適用される税制優遇制度です。
通常、空き家を売却して利益が出ると、以下のように税金が課されます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得に対して、
- 所有期間5年以下 → 約39%(短期譲渡)
- 所有期間5年以上 → 約20%(長期譲渡)
の税率がかかります。
しかし、この特別控除を利用すると、最大3,000万円までの譲渡所得が非課税となります。つまり、3,000万円以下の利益であれば、税金がゼロになる非常に大きなメリットがあります。
特別控除の適用条件(築年・耐震・売却期限など)
この特例はすべての相続空き家に適用されるわけではなく、いくつかの条件があります。
主なポイントは以下のとおりです。
適用対象となる建物の条件
- 被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた自宅であること
- 1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅であること
- 相続後に取り壊して更地で売る、または耐震改修をして売却すること
売却の期限
- 被相続人が亡くなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
その他の条件
- 相続開始から売却までの間に貸し出したり、居住したりしていないこと
- 売却価格が1億円以下であること
これらをすべて満たした場合に、「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用されます。つまり、「古い家をそのまま売る」ではなく、取り壊しや耐震改修を行うことがポイントです。
なお、横浜市では旧耐震基準の住宅が多く、特例の対象になりやすいため、「古い実家を相続してどうするか迷っている」方は、売却前にこの特例の適用可否を確認する価値があります。
控除を受けるために必要な書類と確定申告の流れ
この特例を受けるには、確定申告での申請が必須です。
確定申告の際に、以下の書類を提出する必要があります。
主な必要書類
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 被相続人の住民票の除票(死亡時の住所を証明するもの)
- 耐震基準適合証明書または取壊し証明書
- 相続を証明する戸籍謄本・遺産分割協議書
これらの書類を揃えた上で、相続人が自ら申告します。特に「耐震基準適合証明書」や「取壊し証明書」は発行までに時間がかかる場合があるため、早めの準備が大切です。
また、申請を誤ると控除が適用されないこともあるため、不動産会社や税理士に相談しながら進めるのが安心です。
この「相続空き家特別控除」は、使えるかどうかで数百万円単位の差が出る重要な制度です。相続した空き家を売却する前に必ず確認し、条件を満たすように準備しておきましょう。
横浜で相続空き家を売却する際に注意すべき3つのポイント
相続した空き家を売却するには、通常の不動産取引にはない相続特有の手続きや注意点があります。登記や名義、相続人同士の合意が整っていないと、スムーズに売却できないだけでなく、思わぬトラブルに発展することも。
特に横浜のように土地の区画や建物の歴史が古いエリアでは、登記や境界の不備が残っているケースも多いため注意が必要です。
ここでは、売却前に必ず確認しておきたい3つのポイントを解説します。
相続登記が未完了だと売却できない
まず最初の注意点は、相続登記を完了していないと不動産を売却できないということです。登記簿上の名義が亡くなった方(被相続人)のままでは、売買契約を結ぶことができません。
売却するためには、
- 相続人を確定させる(戸籍謄本で確認)
- 遺産分割協議で誰が不動産を相続するか決める
- 相続登記を行って名義を相続人に変更する
という流れが必要です。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続開始から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。
売却を検討している場合は、まず登記の状態を確認し、司法書士など専門家に相談して早めに手続きを進めましょう。
複数の相続人がいる場合のトラブルを防ぐ方法
相続人が複数いる場合、全員の合意がなければ不動産の売却はできません。1人でも反対する人がいれば契約が成立しないため、家族間の意見調整が非常に重要です。
よくあるトラブルとしては、
- 「売りたい人」と「残したい人」で意見が分かれる
- 売却価格や分配金額に納得がいかない
- 相続人の1人が遠方に住んでおり連絡が取れない
といったケースがあります。
こうしたトラブルを防ぐには、まず全員で遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。
協議書に「この不動産を誰が相続し、売却後の代金をどのように分けるか」を明記しておけば、後から揉める心配がありません。
また、話し合いがまとまらない場合は、不動産会社や弁護士・司法書士を交えて中立的に調整するのも効果的です。
名義変更と遺産分割協議の正しい進め方
相続空き家を売却する前には、名義変更と遺産分割協議の手続きを正しく行うことが欠かせません。
遺産分割協議では、
- 相続人全員の参加が必要
- 協議の内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成
- 全員の署名・実印押印・印鑑証明書を添付
という流れで進めます。
その後、協議書に基づいて法務局で相続登記(名義変更)を行います。
このときに不備があると、登記が受理されず売却スケジュールに遅れが出るため、司法書士などの専門家にチェックを依頼するのが安心です。
また、横浜市内の一部エリアでは、古い住宅地図や境界資料が不明確な場合もあるため、測量・境界確定を同時に行っておくと、売却時に買主からの信頼度が高まります。
このように、相続空き家の売却では「登記・合意・名義」の3点をしっかり整えることが成功のカギです。事前準備を怠るとトラブルや手続き遅延の原因になるため、早めに専門家へ相談して段階的に進めることをおすすめします。
売却が難しい相続空き家でも諦めない!スムーズに解決する方法
- 老朽化が激しくて売れないかも
- 再建築不可と言われた
- 片付けもできていない
こうした理由で空き家の売却を諦めてしまう方は少なくありません。
しかし実際には、条件の悪い空き家でも売却・買取の方法はあります。
最近では、古い家や再建築不可の土地を専門的に扱う不動産会社や買取業者も増えており、以前なら「売れない」と言われた物件でも、いまは十分にチャンスがあります。
ここでは、売却が難しい相続空き家を解決に導く3つの具体的な方法を紹介します。
老朽化・再建築不可物件でも買取可能な業者を選ぶ
築年数が古い、建物が傾いている、再建築不可──こうした空き家は、一般の仲介市場ではなかなか買主が見つかりにくいのが現実です。
しかし、不動産の買取専門業者なら、そうした“難あり物件”でも購入可能なケースが多くあります。
彼らは再生・転売・土地活用などのノウハウを持っており、老朽化した建物を解体して更地にしたり、リフォームして再販売したりと、再利用を前提に買取を行います。
特に横浜市では、再建築不可の物件や古い木造住宅をまとめて再開発・リノベーションする事例も増加中。「うちの家は古いから無理」と思い込まず、まずは買取査定を依頼してみるのが第一歩です。
残置物や荷物があっても現況のままで売却できる
「相続した家に荷物がたくさん残っていて片付けができない…」
そんなケースでも、残置物をそのままにして売却できる方法があります。
多くの買取業者や相続対応に強い不動産会社では、家具・家電・衣類などの残置物をそのまま引き取る「現況買取」に対応しています。
片付けや清掃を自分で行う必要がなく、高齢の方や遠方に住んでいる方でも、最小限の手間で売却が可能です。
また、専門業者に任せれば、ゴミ屋敷化した物件でも査定対象となるケースがあります。
むしろ、「残置物処分にかかる費用を差し引いても早く手放したい」という場合には、現況のまま売却できる買取ルートが最も効率的です。
横浜の地域密着型不動産会社に相談するメリット
相続空き家の売却では、地域密着型の不動産会社に相談することが成功の近道です。
横浜のように区ごと・駅ごとに地価や需要が大きく異なるエリアでは、地元の市場や再開発情報を熟知している会社でないと、正確な査定ができません。
地域密着の会社なら、
- 地元の買主・建築会社とのネットワークがある
- 市の条例や建築規制にも詳しい
- 相続登記や測量などの専門家(司法書士・土地家屋調査士)と連携できる
といった強みがあります。
特に、古家付き土地や再建築不可物件など「難案件」ほど、地元の実情を理解している業者ほど柔軟に対応してくれます。
「都心の大手では断られたけど、地元の会社ではすぐに買い取ってくれた」というケースも多く、横浜市での空き家売却では、まず地域に根ざした不動産会社へ相談することをおすすめします。
このように、売却が難しい相続空き家でも「再利用」「現況買取」「地元業者」という3つの視点を持つことで、
思いがけない解決策が見つかることがあります。
「無理だ」と決めつけず、まずは現状のまま相談・査定を依頼することが解決への第一歩です。
相続空き家の売却でよくある質問(FAQ)
相続した空き家を売却する際に、よく寄せられる質問をまとめました。
手続き・税金・売却方法など、不安を感じやすいポイントを中心にわかりやすく解説します。
Q1. 相続登記が終わっていなくても売却できますか?
いいえ、相続登記を完了していない状態では売却できません。
不動産の名義が被相続人(亡くなった方)のままでは、売買契約を締結できないためです。
ただし、司法書士や不動産会社に相談すれば、登記手続きを並行して進めながら売却準備を進めることも可能です。
登記が完了すれば、すぐに売却手続きへ移れます。
Q2. 相続した家の名義が複数人でも売れますか?
はい、可能です。
ただし、相続人全員の同意が必要となります。
1人でも反対する人がいると契約が成立しないため、事前に話し合いを行い、「遺産分割協議書」を作成しておくとスムーズです。
不動産会社が間に入って調整することもできますので、早めに相談するのが安心です。
Q3. 相続後、どのくらいで売却するのがいいですか?
目安としては、相続後3年以内の売却をおすすめします。
なぜなら、「相続空き家の3,000万円特別控除」は、相続から3年を経過する年の12月31日までに売却しないと適用されないためです。
また、空き家を長期間放置すると老朽化や税負担が増すため、早めの売却が資産を守るポイントです。
Q4. 古い家でもそのまま売れますか?
はい、築年数が古くても売却可能です。
横浜市内では、古民家やリノベーション前提の物件にも需要があります。
また、建物の状態が悪くても、買取業者なら現況のまま買い取ってくれるケースが多いです。無理にリフォームをするより、まずは現況で査定を受けてみましょう。
Q5. 解体費用はどうなりますか?
老朽化が進んでいて建物を取り壊す場合は、解体費用が必要です。
費用の相場は建物の大きさによりますが、一般的に100万〜300万円前後が目安です。
ただし、買取業者の中には「解体費を差し引いて買取」や「解体費込みでの査定」を行う会社もあります。売却前に見積もりを比較して検討しましょう。
Q6. 税金(譲渡所得税)はどれくらいかかりますか?
不動産の売却益(譲渡所得)には、所得税+住民税で約20〜39%が課税されます。
ただし、相続空き家の場合は「3,000万円特別控除」を利用することで、税金を大幅に減らせる可能性があります。控除の適用には条件があるため、売却前に税理士または不動産会社へ確認することをおすすめします。
Q7. 特別控除は誰が使えますか?
「相続空き家の3,000万円特別控除」は、実際に売却を行った相続人1名のみが利用できます。
複数の相続人がいる場合でも、1つの空き家につき控除を使えるのは1人だけです。
ただし、遺産分割の内容によっては他の相続人にもメリットが及ぶケースもあるため、税理士に確認しましょう。
Q8. 買取と仲介、どちらがおすすめ?
目的によって異なります。
- 少しでも高く売りたい → 仲介
- 早く・確実に現金化したい → 買取
老朽化や残置物が多い場合、買取の方がスムーズです。
横浜市内では、築古や再建築不可物件の買取に強い業者も多いため、複数社の査定を比較して選びましょう。
Q9. 遠方でも売却を任せられますか?
はい、可能です。
現地に行かなくても、オンライン査定・郵送・委任契約などで売却を完了できます。横浜市内の不動産会社の多くは、相続人が他県や海外に住んでいるケースにも対応しています。
現地立ち会いなしで査定・契約を進められるので、安心して任せられます。
Q10. 横浜市内どの区でも対応していますか?
はい、横浜市全18区すべてに対応可能です。
中区・西区などの中心部から、港北区・青葉区・戸塚区・泉区といった住宅地まで幅広くカバーしています。
地域によって相場が異なるため、横浜エリアの不動産事情に詳しい会社を選ぶことで、より高値での売却が期待できます。
このように、相続した空き家は「古くても」「遠方でも」売却可能です。放置せず、専門家に相談して一歩を踏み出すことが、資産を守る最善の方法といえます。
相続した空き家を放置せず、横浜で賢く売却を進めるために【無料相談受付中】
相続した空き家は、「まだ大丈夫」と思って放置すると、老朽化や税負担の増加、トラブルの火種になることもあります。
横浜市でも空き家の増加が社会問題化しており、早めの対応が何より重要です。売却・買取・活用、どの選択をするにしても、まずは現状を正確に把握することから始めましょう。
相続空き家の売却には、登記・税金・相続手続きといった複雑な要素が絡みます。
しかし、流れを理解し、専門家のサポートを受けながら進めれば、スムーズに完了させることが可能です。
特に「相続登記の義務化」や「3,000万円特別控除」などの制度は、タイミングを逃すと損をするケースも多いため要注意です。
横浜で空き家を相続した方は、まず地域に強い不動産会社へ無料相談をしてみてください。
地元の相場や再開発動向を把握している専門業者なら、「売る」「残す」「活用する」それぞれのベストな方法を提案してくれます。
古い家や再建築不可の土地でも、現況のまま買取できる場合もあるため、悩む前に一度、無料査定・相談を利用してみることが最善の一歩です。





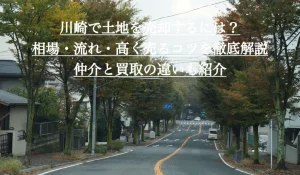
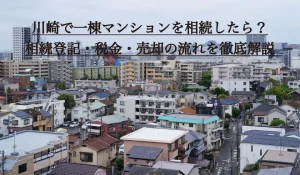
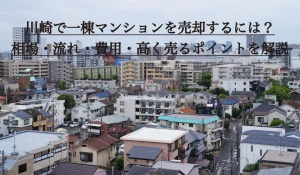
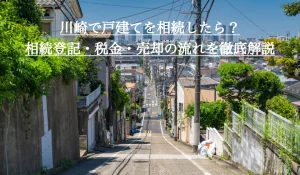
コメント